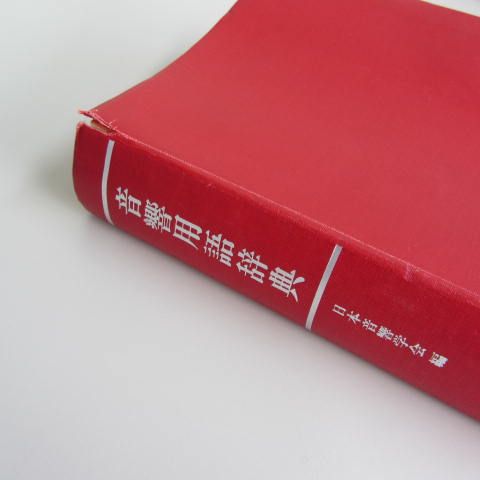■こんにちは!「耳栓ブログ|ae The Blog」の高祖です。
「耳栓ブログ|ae The Blog」では、身近な話題から、
防音、騒音の対策を考えるというコンセプトにそって
提供させていただいています。
ここのところ、ミュージシャンに関する耳の問題について
取り上げてきました。また、「音響外傷」、「騒音性難聴」
等についても知りました。
音響外傷、騒音性難聴について、おさらいした方は
こちらへどうぞ!
■本日は、「耳をライブでの大きな音から守る」という視点から、
日常的に耳にする音が、どれくらいの大きさで
皆さんの耳に、さらされているかについて
お話をしていこうと思います。
■実際、大きな音は、耳に良くないということは
頭では、わかるとはいえ、どのような音が
どれくらい大きいかということになると
わかりにくいものです。
特に、日常的に耳にしているものについては
大きな音に実際はさらされていても
意識には上がってこないものです。
■しかし、意識に上がってこないからといって
耳への負担が低くなっているかと言えば
そうではなく、やはり負担は続いている形となります。
ですので、一度、客観的な視点から
あなたの耳にさらされている音の環境を考えなおして見ることも
良いかと思います。
■先日、日常的に耳にしている音の大きさを
簡単に示している表などないか
いろいろ探してみました。
中でも、わかり易かったのが
岡山市環境白書(平成23年度版)
で紹介されている「騒音の大きさの例」です。
表を抜粋してみました。
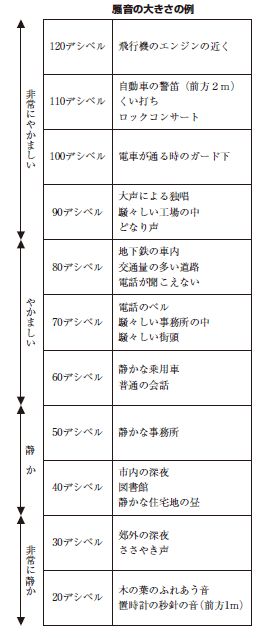
こちらには、かなり噛み砕いたかたちで
日常的に耳にする音の大きさを
説明しています。
■音の大きさは、ご存じの方も多いかもしれませんが
dB(デシベル)で表します。
表に示してある音を幾つか取り上げてみると
普通の会話で・・・60デシベル
図書館で ・・・40デシベル
置き時計の秒針・・20デシベル
それに対して、
ロックコンサート・・110デシベル
です。
■いままでに、エリック・クラプトンが・・・スティングが・・・、
フィル・コリンズが・・・と
多くのミュージシャンが耳の問題を抱えているという記事を
書いてきましたが(興味がある方は・・・こちら)
エリック・クラプトン
ロジャー・ダルトリー
スティング
フィル・コリンズ
確かに、こうやって比較してみると
110デシベルの音に、常にさらされている状況では
無防備であれば、耳の調子も悪くなってしまうことも
わかるような気がします。
■実際には、例に上げてある音の大きさは参考値で、
実際には、その場合、場合によって
大きさが違ってきます。
例えば、ロックコンサートで・・・110デシベル
ということですが、
パンクやメタルでは、もっと数値が高いでしょう(?)。
これも、それぞれのバンドによりますが・・・
私の好きな The Muffs というパンク(?)バンドでは
かなり大きいはずです!
■それから、何よりも・・・
スピーカーからあなたまでの距離
これによるものが大きいかと思います。
私も、若いころは、喜び勇んで
最前列に陣取って、ライブを満喫してものでしたが
スピーカーは、ほんとに耳の真横
ライブ後に、耳があまり聞こえず
友人と話するのが大変だった覚えがあります。
■これから、夏にかけ、
ロックフェス、野外フェスがたくさん開催されていきます。
みなさんの中でも、すでに予定に入れている方も多いのでないでしょうか?
バンドのライブ、コンサート、ロックフェスに行かれるときは
今回ご紹介した日常的によく耳にする音の大きさの参考値を
頭の隅においていたほうが良かもしれません。
■大好きな音楽・・末永く楽しみたいですもんね!
私は、若い時の過ち(?)はあったとはいえ、
今は、自分の耳を、音に関する研究開発者として
自分の大切な「商売道具」として大事にしているつもりです。
聞こえていた音が、聞こえなくなるって結構寂しいことだと思うので・・・
■ご存じの方もいるかもしれませんが・・
「ae The Blog」では、
ライブの時に、ピッタリの耳栓 MusicSafe Proを取り扱っていますので
ご興味がある方は、ぜひ、こちらのライブ用耳栓の詳細をご覧になって下さい。
少し紹介させていただくと・・・
耳栓MusicSafe Proは・・・
聞こえてほしい音が聞こえるところが普通の耳栓と違います!
つけ心地の柔らかさも長時間のライブ向け
だから、ライブ用耳栓としてピッタリです。
ヨーロッパ、アメリカで人気の耳栓です!
日本初上陸の製品です。
■それでは、次回も「防音」、「騒音対策」と
考えて私の気になる話題をお届けします。
それでは、本日はありがとうございました。
■「ae The Blog」では
こちらから情報を発信していくだけでなく、
みなさんの周りでの「防音」、「騒音対策」
などについて情報も取り上げて、みんなでいろいろと考えていき
共有させていただきたいと考えています。
何かコメントなどあれば、お気軽に
info@sounds-lab.comまでお問い合わせください。
それでは、次回まで!